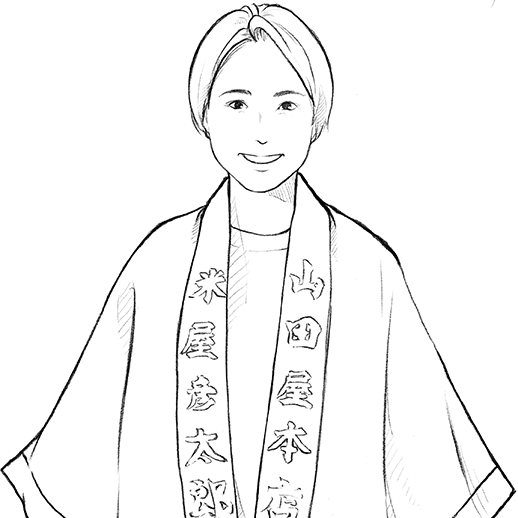お米は生鮮食品です。お米も鮮度が命!
新米は、9月下旬から10月頃に収穫されます。収穫されたばかりのお米(籾)は、水分が多いので(20%~30%程)、乾燥機に入れてゆっくりと乾燥させます。このとき急いで乾燥させるとお米にひびが入って味が落ちてしまうので水分量が15~16%になるように注意して乾燥させます。この乾燥工程は、お米の品質管理のなかで非常に重要で、少しでも水分量が多すぎるとカビが発生する原因となり、逆に少ないとヒビ割れを起こし、品質や食味に悪い影響が出てしまうのです。

さて、ここまでの説明だけで判断すると、お米は「乾物=保存食」と思われるかもしれません。しかし、お米は「生鮮食品」なのです。私たち米屋に玄米として届くころには、約15%程度水分があります。生産者さんから、万全の状態で入荷してきたお米を、米屋は1年間通して、おいしくお客様へお届けするために、正しい保存に努めます。室温が15度以下、湿度は50~60%で保存し、鮮度と品質を保っているんです。
ご家庭のお米の保存でお願いしたいことは、密閉容器に入れて、比較的涼しい場所を選び、湿度が低く、直射日光が当たらないところが適しています。貯蔵する温度を10℃以下に下げると、米の酸化速度を遅らせることができるので、特に梅雨時期や夏場は、冷蔵庫がおすすめです。また、定期的に米びつの掃除を行うことで、カビの発生や防虫対策にもなります。特に、暑い夏場などは2~3週間くらいで食べきれる量を購入しましょう。
炊飯の心得は「研ぎ」「浸漬」「ほぐし」
おいしくお米を炊き上げるために、必要なポイントは3つ。

炊飯の心得 その1「研ぎ」
計量したお米をお釜に入れ、洗米します。軟水のミネラルウォーターや浄水器のお水などをお米が全部浸るぐらい入れ、手で軽くお米を2~3回転させ、その後素早くお水を全部捨てましょう。特に最初の水は、比較的吸収し易く、お米に残っているヌカの匂いなどが、お米に移らないように、手早くお水を捨てる事がポイントです。このあとは「お米に水を注ぎ、軽く混ぜたらその水は捨て、しっかり水を切ってからお米を研ぐ」という作業を2~3回、繰り返します。
お米を研ぐ際、水を入れたまま状態で行う人もいるようですが、お米は「洗う」のではなく「研ぐ」といいます。米粒が水の中で泳がないよう、水をしっかり切れば、米粒同士が軽くぶつかりあうその摩擦で研ぐことができます。研ぐときの手は「クマの手」で!お米はとてもデリケート。お米に無駄な力がかからない、この“クマの手”をするのがお勧めです。米粒の中に手を入れたら、クルクル円を描くように回しましょう。20回ほど円を描いたら、水を入れ、出てきた米ぬかを洗い流します。これを2~3回繰り返します。

炊飯の心得 その2「浸漬(しんせき)」
次に「浸漬(しんせき)」をします。浸漬とは、お米を水に浸すことです。水の量は、最初に計ったお米のグラム数の1.45倍。300g(約2合)のお米なら435ccのお水で浸漬してください。品種によっても、お水の適量は変わりますので、米穀店やお米マイスターに相談してみてください。炊きあがりの好みは、ご家庭それぞれだと思いますので、一度規定の水分量で試してから、お好みの水加減を見つけるのが良いでしょう。
水温によって浸漬時間は変わります。夏場(水温25度前後)は30分、冬場(水温5度前後)は1時間が目安。昔は「新米は水分量が多く、古米になると減ってくるので、時期によって水の量を変える」といわれましたが、今は保存の環境や水分管理の技術が上がっているので、特に気にする必要はありません。
炊飯器にお米をセットした状態で浸漬させて大丈夫ですが、夏場は水が痛んでしまう可能性もあるので、気をつけてください。もし夜に研いだお米を朝に炊く場合は、冷蔵庫の中で冷やしながら浸漬させるようにしましょう。

炊飯の心得 その3「ほぐし」
「ほぐし」は、お米のおいしさに1番関わっているといっても過言ではありません。炊き上がったらすぐにほぐす!炊き上がったごはんをそのままにしておくと、蓋についた余分な水分がごはんに落ち、べちゃっとした食感となり、食味を悪くします。
ほぐし方は、まず、お釜の中のごはんを十字に切り、ごはんを底の方から4分の1ずつ返します。ごはん粒をつぶさないように、蒸気を逃がしながら空気を含ませる感じで、優しくほぐします。こうすることで、粒表面がはっきりして粒感のある美味しいごはんに仕上がります。
以上、3つのポイント「研ぎ」「浸漬」「ほぐし」をマスターすると、ごはんの味がかわってきます。美味しくたべるコツを掴んで、いつものお米をもうワンランクアップしたご飯に炊き上げましょう!
めいぶつチョイスで買える米・雑穀の商品一覧を見る
※本記事はにほんものストアにて2021年9月30日に公開された記事の転載です。記事の内容は掲載当時の情報です。