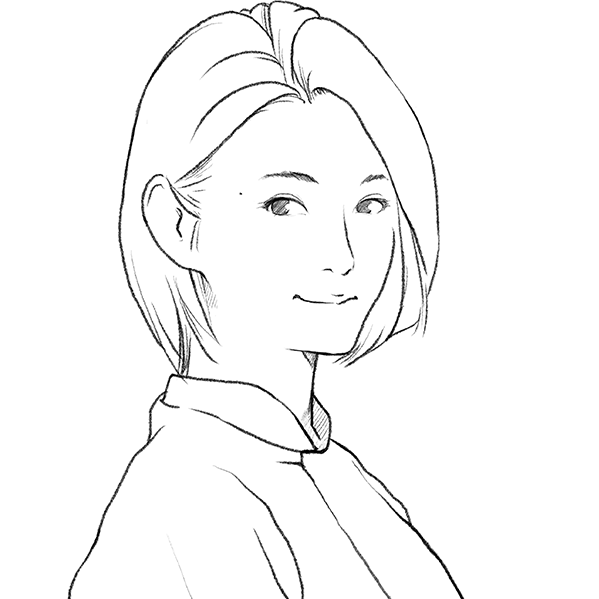実は日本は塩の技術の先進国
一言で塩といっても塩にも種類があります。原料別に、おおまかに分けて5つに分類できます。このうち世界的に主流なのは岩塩で、世界の塩の生産量の約6割は岩塩が占めています。日本でもパキスタン産のピンク色をした岩塩が有名ですね。しかし日本には残念ながら岩塩層や塩湖が存在せず、塩の原料となる資源が海水とほんの少しの地下塩水しか存在しません。そのため、日本人にとって塩といえば海水塩のイメージが強いのですが、これは世界的にも珍しいことなのです。
しかし塩資源に乏しい分、逆に日本では、「塩分濃度が3%しかない海水からいかに効率的に質の良い塩を作るか」ということに心血が注がれてきた歴史があり、いわば日本のものづくりの魂がこもっている分野でもあります。そのおかげで、日本は今では世界に誇れる製塩技術を持ち、その技術が輸出されたりもしています。 現在、日本全国で製塩を行っている場所は約600カ所にものぼり、純国産の塩だけでも1000種類以上の塩が生産されています。これほど多くの種類の塩が多彩な製法で作られているのは世界広しと言えども日本だけ。素材の味を大切にするシンプルな味付けが多い和食文化が食文化のベースであることも関係しているのでしょうが、日本は塩のおいてはちょっと特殊な国なのです。

日本の塩の主流は味わい多彩な「海水塩」
私たち日本は岩塩や湖塩がなく、その代わりに、この海水塩の特徴を最大限に活かした塩作りを行ってきたわけです。そして日本は海に囲まれた島国なので、全国各地で塩づくりが行われてきました。
よく「岩塩と海水塩でどう味が違うのか?」と質問されるのですが、これって非常に難しい質問なのです。なぜなら、塩の味はどんな原料を使ったかと、どうやって作ったかのかけ算で決まるから。でも、ちょっとした傾向はあります。それは、岩塩に比べて海水塩のほうが、「味わいが多彩」ということです。詳しくは追々解説するとして、ちょっとだけご説明しましょう。

日本の塩はコレ!
分解すると「母なる水」と書くことからもわかるように、海水には地球上の元素がすべて含まれています。製法にもよりますが、ナトリウム以外のミネラルも多く含んだ塩ができやすく、それがしょっぱさ以外の味として感じられます。しょっぱさの強い塩から非常にまろやかな塩まで作ることができます。そして製法によって形も様々に変化するので、溶けるスピードや食感なども変化に富んだものができます。

世界の主流
長い年月を経る間に、ミネラル別に結晶する層が分かれます。岩塩を採掘する時は主に塩の主成分であるナトリウムが結晶した部分を狙って採掘するので、ナトリウム構成比が高くなる(しょっぱさが強くなる)傾向があります。巨大な一塊の結晶を爆破して粉砕して掘り出すので、結晶の形は均一ではなく不均等になります。
めいぶつチョイスで買える調味料・油の商品一覧を見る
※本記事はにほんものストアにて2021年3月15日に公開された記事の転載です。記事の内容は掲載当時の情報です。